※基本的にストーリーのネタバレはありませんが、発売前時点で未公開の情報も含まれているため、ご注意ください。
広告
2023年6月22日に発売予定のプレイステーション5(PS5)用ソフト『ファイナルファンタジーXVI』(以下『FF16』)。本作は、スクウェア・エニックスの看板タイトルのひとつとして知られる『ファイナルファンタジー』シリーズの最新作で、シリーズ初のアクション・RPGとなっている。
▼『FF16』攻略&解説まとめ
『ファイナルファンタジーXVI』(PS5)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
関連記事
これさえ見ればわかる『FF16』のすべて。『FF』初体験もファンも。ゲーム初心者も玄人も。“しっとり”好きも“激アツ”好きも。極上の物語とアクションの両方が味わえる“リアル”な『ファイナルファンタジー』
これを見れば『ファイナルファンタジーXVI』(FF16)のすべてがわかる。『FF』シリーズの最新作の注目ポイントや気になる要素をまとめてお届け。
本作はシリーズ初の本格アクションゲームだが、アクションゲームが好きな人はもちろん、ストーリーを重視したい人や、アクションゲームが得意ではない人でも楽しめるゲームとして、数多の工夫が凝らされ、丁寧に開発されている。
そんな本作を遊ぶ上で覚えておきたいマメ知識を、フィールド・準備編で10個、バトル編で10個ずつピックアップ。あなたのヴァリスゼア冒険に役立ててほしい。
目次閉じる開く
フィールド・準備編
1:L3ボタン長押しで進むべき道がわかる 2:目的地はマップを見て調べよう 3:エリアマップとワールドマップは行き来できる 4:クエストは“+”アイコンを優先 5:装備は積極的に買い替えよう 6:強敵が落とす素材は出し惜しみせず武器の作成に使おう 7:経験値、AP、ギルの獲得量がアップするアクセサリが存在する 8:使ったAPはリセット可能。自分なりのベストな組み合わせを探そう 9:リプレイモードで取り忘れたアイテムを回収可能 10:フィールドを探索してみよう
バトル編
1:敵の攻撃は引き付けすぎず早めに回避 2:ウィルゲージを減らしてテイクダウンを狙う 3:マジックバーストの役割と練習方法 4:特殊な行動を取る敵を優先して倒す 5:いちおしフィート“タイタンブロック” 6:おもな回復手段はアイテムかリミットブレイク 7:メニュー画面からもアイテムが使える 8:リミットブレイク発動中は戦闘不能にならない 9:リトライ時はノーペナルティで回復アイテムが補充される 10:サポートアクセサリで立ち回りを学ぼう
フィールド・準備編
1:L3ボタン長押しで進むべき道がわかる
L3ボタンを長押しするとメインストーリーの目的地を示すアイコンや進むべき方向を知ることができる。
本作ではフィールド上でシームレスに戦闘が始まるため、戦闘を終えた後にどちらを向いているかわからなくなることもしばしば。
フィールドの移動中にミニマップのようなものは表示されないので、迷ったときや方向感覚が狂ったときはL3ボタンを押してナビゲーションを起動する癖をつけるといい。
物語を進めるとL3ボタン長押し時にトルガルがナビゲーションをしてくれるようになる。
また、探索中に“正規ルート”以外をくまなく探索したいという人もいるだろう。そういう人もこのナビゲーションを活用し、示す方向と別の方向に行けば、宝箱などを撮取りすことが減るかもしれない。
2:目的地はマップを見て調べよう
フィールドでは高低差があるマップなど、入り組んだ構造の場所も多い。そのため、画面に表示されている目的地のアイコンに一直線で向かおうとしてもたどり着けないことも少なくない。
コントローラーのタッチパッドを押すと現在のエリアマップが確認でき、自分の現在地や目的地、クエストの発生場所、ショップなどの場所が見られる。ナビゲーションとエリアマップを併用すれば、迷う心配はない。
3:エリアマップとワールドマップは行き来できる
エリアマップを表示しているときにオプションボタンを押すと、瞬時にワールドマップ画面に遷移可能。逆に、ワールドマップ画面でタッチパッドを押すとエリアマップが見られる。
ワールドマップはメニューの項目のひとつだが、スキップトラベルがしたいときはエリアマップからアクセスしたほうが手早いことも多いことを覚えておこう。
4:クエストは“+”アイコンを優先
フィールドやエリアマップで、“!”アイコンが付いている場所に行くと、クエストが受注できる。依頼をこなせばさまざまな報酬がゲットできるので、ぜひとも挑戦しておきたいところ。
アイコンが“!”ではなく“+”になっているものは、持てる回復のアイテム数の上限解放といった重要な報酬が用意されている。クエストなどの寄り道要素は後回し、というプレイスタイルの方も“+”アイコンのものは見かけたらクリアーしておくことをおすすめする。
また、クエストはアジトの“協力者連絡窓口”で確認でき、最寄りのオベリスク(ファストトラベルワープ地点)にも直接移動できるので、覚えておくといい。
5:装備は積極的に買い替えよう
装備のおもな入手経路は、ショップでの購入、もしくは鍛冶屋での作成のふたつ。武器や防具は、物語を少し進めるたびによりよいものが販売されていくので、その都度より高性能なものに買い替えるといい。
6:強敵が落とす素材は出し惜しみせず武器の作成に使おう
物語の節目で戦う強敵が落とす見慣れないアイテムは、武器の素材であることが多い。用途は武器の作成に限定されるので、出し惜しみせずに新たな武器の作成をおこなって構わない。
7:経験値、AP、ギルの獲得量がアップするアクセサリが存在する
ある程度物語を進めると、隠れ家にあるカローンのショップで、経験値、AP(アビリティポイント)、ギルの獲得量がアップするアクセサリ3種が販売されるようになる。追加されるのは、アクセサリタブの最下段なので、マメにチェックしてクライヴ強化の役に立てよう。
8:使ったAPはリセット可能。自分なりのベストな組み合わせを探そう
アビリティの習得や強化、およびフィートの強化に使ったAP(アビリティポイント)は、何度でもリセットできる。そのため、アビリティの強化は積極的に行って構わない。新たな召喚獣の能力を得たら、隠れ家でのトレーニングと併用して、手持ちのAPの許す限りさまざまな組み合わせを試してみよう。
迷ったときに役立つ“おすすめ習得”。「何を選べばいいかわからない!」という人は使用するといいだろう。少しでも強化したい場合は、できるだけ自分で使うアビリティを決めて、集中的に強化することをおすすめする。とくにおすすめのアビリティに関しては、バトル編で紹介するのでそちらも参考に。
9:リプレイモードで取り忘れたアイテムを回収可能
隠れ家のアレテ・ストーンで遊べるリプレイモードでは、クリアー済みのステージを何回でも遊べる。リプレイモードでは、開けた宝箱が復活することはないが、取り忘れた宝箱はそのまま。初プレイのときはクリアーを優先し、強くなってからじっくりとステージを探索する、という遊び方もできる。
10:フィールドを探索してみよう
ストーリーを進めていけばおのずとすべてのエリアを訪れることにはなる。一方で、各エリア内は広大でストーリーには関係がない場所もたくさん用意されている。そういった場所には、リスキーモブがいたり、クロノス石塔群と呼ばれるチャレンジ要素があったりと多くの発見があるはず。
エリアマップをじっくりと確認し、足を踏み入れていない(地形が見られるようになっていない)場所がないかを探し、実際に訪れてみよう。
バトル編
関連記事
【FF16攻略】バトルの立ち回り基礎編。基本アクション、敵の攻撃を回避する“ドッジ”の使いかた、戦いかたのコツなど、役立つ知識まとめ
ファイナルファンタジーXVI』(FF16)のバトルで役立つ基礎知識を紹介。敵の攻撃を回避する“ドッジ”の使いかた、戦いかたのコツなど、役立つ知識まとめ。
1:敵の攻撃は引き付けすぎず早めに回避
バトルのいちばんの基本は、相手の攻撃を避け、その隙を突いて反撃すること。ほぼすべての敵の攻撃には予備動作があるので、それに合わせて回避をするのがセオリーだ。
紙一重での回避に成功すると、“プレシジョンドッジ”となってチャンスの幅は広がるが、引き付け過ぎると回避が間に合わずに攻撃を受けてしまう。初心者の人はまずは、少し早めに回避するくらいの気持ちでボタンを押し、攻撃を避けられればよしとしよう。
プレシジョンドッジの判定もそれほどシビアではなく、早めの回避で発動してくれることも多い。最初は避けることを優先して早めの回避を行い、敵の行動パターンが読めてきたら徐々に回避のタイミングを遅らせてみよう。
2:ウィルゲージを減らしてテイクダウンを狙う
体力が多い強敵とのバトルでは、いかにテイクダウンを奪うかがカギ。なぜなら、テイクダウン中は相手が長時間無防備になり、大ダメージを与えるチャンスとなるからだ。
ウィルゲージは、HPと同様に攻撃を当てることで減らせる。アビリティによっては、ダメージは控えめだがウィルゲージを減らしやすい、といったものも存在し、そのバランスはアビリティの画面の★の数で確認できる。
装備するアビリティは、ダメージとウィルゲージのバランスを考えよう。また、下で紹介するマジックバーストもウィルゲージを減らしやすい重要なアクションなので、ぜひともマスターしておこう。
関連記事
【FF16攻略】“召喚獣アクション”まとめ。アビリティの効果や範囲、強化による変更点、MASTER化に必要なポイントなどを解説
『ファイナルファンタジーXVI』(FF16)に登場する召喚獣アクションを細かく掲載&解説していく。
3:マジックバーストの役割と練習方法
マジックバーストは、攻撃(□ボタン)がヒットした瞬間に魔法(△ボタン)を押すと発動するテクニカルなアクション。□、△、□、△……とタイミングよく押していくことで、武器と魔法による攻撃をつぎつぎと放ち、効率よくダメージを与えられる。
しかも、マジックバーストはさきほど紹介したウィルゲージも減らしやすい攻撃になっているので、強敵相手にも有効な攻撃手段となっている。
練習は、隠れ家にあるアレテ・ストーンのトレーニングでおこなうのがおすすめ。設定で、△ボタンを押すとマジックバーストが発動するタイミングを表示させられるので、いつボタンを押すべきかが一目瞭然。
4:特殊な行動を取る敵を優先して倒す
敵の群れの中には、回復魔法のケアルや強化魔法のプロテス、ブレイブ、ウォークライなどを使用する者が紛れていることがある。これらの魔法を受けた敵は、通常よりも倒すのがたいへん。魔法が使われているようなら、まずは術者を探して倒そう。
魔法が使われると画面上部に魔法名が表示。術者はクライヴから距離を取っていることが多い。
関連記事
【FF16攻略】“プロテス”や“ブレイブ”、“ガード”などの特殊な行動をとる敵への対処法
『ファイナルファンタジーXVI』(FF16)のバトルで“ガード”や“ケアル”、“プロテス”など、特殊な行動をとってくる敵への対処法を紹介する。
5:いちおしフィート“タイタンブロック”
タイタンのフィート“タイタンブロック”は、攻撃を防御し、リミットブレイクゲージを上昇させる使い勝手がいい性能となっている。回避が苦手な人はひとまず“タイタンブロック”を使用して、敵の挙動を見定めるべし!
攻撃を引き付けてガードを成功させるとプレシジョン・ブロックに強化され、通常では防げない攻撃もガード可能になり、リミットブレイクゲージ上昇量も増加。さらに、最大3発まで追加攻撃を放つことができるようになる。
関連記事
【FF16攻略】おすすめの召喚獣アクションセットまとめ。アビリティ強化やMASTER化の解説。編成に迷ったときのおともに
『ファイナルファンタジーXVI』(FF16)で召喚獣アクションのオススメの組み合わせを紹介。さらに召喚獣アクションで使用するアビリティの強化とMASTER化を解説する。
6:おもな回復手段はアイテムかリミットブレイク
クライヴは回復魔法を習得しないので、減少したHPはアイテムで回復することになる。初期状態の最大所持数は、ポーションは4つ、ハイポーションは3つ。フィールドやステージ内に落ちていることは多いが、隠れ家や街に入るたびに最大所持数まで補充することをお忘れなく。
また、ある程度物語を進めると発動可能になる“リミットブレイク”にはHPを徐々に回復する効果がある。アイテム節約を目的として、ゲージがたまり次第ザコ相手でも積極的に使っていこう。
7:メニュー画面からもアイテムが使える
方向キーに対応したアイテムショートカットに登録できるアイテムは最大で3つで、回復アイテムのポーションとハイポーションは最初から登録済み(後から変更可能)。消費アイテムには、攻撃力を高める"ちからの薬"、一定時間リミットブレイクゲージを上昇させる"英雄の薬"など、戦闘中に役立つアイテムも多数用意されているので、ショートカットに登録されていないアイテムを使いたくなったらメニュー画面を開こう。
8:リミットブレイク発動中は戦闘不能にならない
“リミットブレイク”発動中は、攻撃性能が大幅にパワーアップし、HPが徐々に回復し続ける。加えて、“戦闘不能にならない”というなんとも頼もしい能力も備わっている。リミットブレイクは、こちらの攻撃動作中だけでなく、ダメージリアクションを取っている最中でも割り込んで発動可能。「ヤバい!」と思ったらとりあえず発動(L3ボタン+R3ボタン)するといい。
9:リトライ時はノーペナルティで回復アイテムが補充される
クライヴのHPがゼロになりゲームオーバーになると、リトライ、もしくはタイトル画面へ戻るかの選択画面になる。リトライを選択すると、直前にオートセーブされた再開地点からゲームがスタートし、再開時にはポーションとハイポーションが最大所持数まで補充される。
さきほどは隠れ家や拠点でアイテムを補充しようとは言ったものの、リトライ目当てで頭を空っぽにして突き進むのもアリだ。
10:サポートアクセサリで立ち回りを学ぼう
サポートアクセサリの《オートアタック》の指輪は、□ボタンを連打するだけで装備中のアビリティを駆使して、多彩な動きを見せてくれる。「新しいアビリティは習得したものの、どういう風に使えばいいかわからない……」とお悩みの方は、いったん《オートアタック》の指輪でどう使っているのかを見てみるのもいいかも。
▼『FF16』攻略&解説まとめ
プレイステーション5 “FINAL FANTASY XVI” 同梱版の購入はこちら (Amazon.co.jp)
...以下引用元参照
引用元:https://www.famitsu.com/news/202306/22305476.html




![任天堂 【Switch】Nintendo Switch Sports(スイッチスポーツ) [HAC-R-AS8SA NSW スイッチスポーツ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1718/4902370549263.jpg?_ex=128x128)
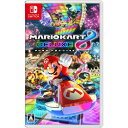






![コナミデジタルエンタテインメント 【Switch】桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 [HAC-P-ATKTA NSW モモタロウデンテツ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1432/4988602173222.jpg?_ex=128x128)


![任天堂 【Switch】スーパーマリオブラザーズ ワンダー [HAC-P-AQMXA NSW ス-パ-マリオブラザ-ズ ワンダ-]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0075/4902370551587.jpg?_ex=128x128)

