2024年4月25日にスクウェア・エニックスより発売予定の『サガ エメラルド ビヨンド』。対応ハードはNintendo Switch、プレイステーション5、プレイステーション4、PC(Steam)、iOS、Android。
広告
本記事では『サガ』シリーズ20作目となる、『サガ エメラルド ビヨンド』の先行レビューをお届け。序盤のプレイを通して感じたことや、ゲームシステムなどを解説していこう。
なお、遊んだバージョンは開発中のものなので、製品版とは異なる場合がある。
『サガ エメラルド ビヨンド』先行プレイ動画。関西弁大学生、ネコを集める魔法少女、歌姫メカの序盤を体験
『サガ エメラルド ビヨンド』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
『サガ エメラルド ビヨンド』(PS5)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
『サガ エメラルド ビヨンド』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
『サガ』らしい多彩な世界観
プレイヤーは6人5組の主人公からひとり(ボーニー&フォルミナを選んだ場合はふたり)を選び、冒険をくり広げていく。主人公それぞれの物語がありつつ、道筋を自由に選んで冒険を楽しめる『サガ』シリーズらしいシステムが踏襲されている。
遊んでみた印象としては、『サガ スカーレット グレイス』(以下、『サガスカ』)にかなり近い。ゲームの雰囲気やバトルシステムに共通するものがありながらも、さらに遊びやすく、奥深いバトルが味わえるようになった印象だ。
立ち絵とセリフで進行していく会話シーンは『サガスカ』そのもの。
『サガスカ』は王道ファンタジーの世界観でまとまっていたが、本作の舞台となる複数の“ワールド”の世界観は、中世ファンタジーやSF、現代的なものなど、とても幅広い。シリーズファンは、“『サガスカ』が『サガ フロンティア』になったようなゲーム”だと思えばイメージしやすいだろう。
それでいてゲームボーイ『サガ』3作品を感じさせる要素や、『ロマンシング サガ』シリーズを彷彿とさせるポイントもあり、『サガ』シリーズ集大成のような作品になっていると感じた。
2Dの絵でスポットが表現されている点も『サガスカ』に似ている。
ワールド間を移動するパートでは、3Dフィールドを歩き回るシーンもある。
バトルシステムは『サガスカ』のものをパワーアップさせたような印象。
ストーリー進行はスムーズ
本作では地続きになった大きなフィールドを旅するのではなく、“連接領域”という場所を経由し、さまざまな世界を行き来しながら冒険していく。主人公ごとに旅の目的は異なるが、訪れるワールドはだいたい共通している(訪れる順番、出現順番などは変わるようだ)。
それぞれのワールドでは、『サガスカ』のように、スポットを訪れて会話をくり広げたりしていく。本作には“スキャン”というシステムがあり、一度スキャンを行えば、目的地やサブ要素など、イベントスポットが“ヴィジョン”としてすべて開示されるため、どこに何があるのか自分で探し回るような、探索はしなくていい。
基本的には、まずはスキャンして、どのイベントをこなしていくのか選択しながら進んでいくのが本作の基本だ。エリアにもよるが、目的地がすべて表示されるゆえに、ギミックのあるマップ以外では迷うことはなく、とても遊びやすかった。
また、ヴィジョンは色で分けられており、緑色がメインストーリー、青色はサブ、赤色はバトル専用と、何をする場所なのかも明確にわかる。メインを進めずにサブ要素を網羅したり、バトルで育成してからメインを進めたりと、プレイスタイルに合わせた選択のしやすさも感じられた。
連接領域は、ワールド選択のような場所。
スキャンするとイベントスポットがすべて明示され、場所もわかるし、どれがサブなのか本筋なのかもわかる。
前述の通り、世界観は本当に多彩で、ファンタジーの中にメカや現代人、モンスターの仲間などが入り乱れ、もはやまとまりのない感じがまさに『サガ』といったところ。仲間になるキャラクターも個性豊かで、物語の中で多数の仲間と出会っていく。
ちなみに、バトルメンバーの5人以外は、控えとして待機する。そのため、仲間を加入させたり脱退させたりという管理は必要なし。また、仲間ひとりをサポートメンバーとして置くことができ、キャラクターによってそれぞれに異なる効果を得られる。
メカとエイリアンが混在するSFワールド。
現代の日本のようなワールド。
ゴシックホラーなワールドなども存在した。
旅の中では“せんせい”と出会うことがあるが、この“せんせい”はバトル用のサブミッションのような存在。達成していくと、報酬をゲットできる。また、“せんせい”を通して控えメンバーを修行させることもでき、バトルに参加させずとも育成が可能だ。
どこかで見たことがあるような、せんせい。とかしそう。
修行に出すと、一定回数バトルをこなすことでキャラクターを強化できる。
物語の中では“リトグラム”といった、謎解きパズル要素もある。
知るほどハマるタイムラインバトル!
戦闘は、フィールドでエンカウントすることはなく、すべてイベントで発生する。『サガスカ』と同じように、ゲームのメインはバトルにあり、独特のバトルシステムを楽しむことこそが、本作最大の魅力だと感じた。
タイムラインに沿って、敵味方が順番に行動していくのは『サガスカ』と同じ。敵が行動する前に敵を倒したり、行動順の早い攻撃を選んで、敵より先に動き出すなど、タイムラインを使った戦略が楽しめる。パーティー全体で共有するポイント“BP”を消費して、技や術をくり出していくという仕組みも踏襲されている。
画面下が行動順を表すタイムライン。下に並ぶ緑マス(味方)、赤マス(敵)が連携範囲。黒マスは連携しない。
その中で、『サガ』シリーズおなじみの“連携”などのシステムが絡んでくる。本作の行動(技・術)には“連携範囲”というマスが存在し、タイムライン上で味方と味方の連携範囲のマスをつなげると、“連携”が発生し、与えるダメージがアップ。いかに連携していくのかを考えるのが、バトルの基本となっている。
多数の仲間と連携することで、“連携率”がアップし、威力も上昇。さらに、連携率が150%以上に高まると“オーバードライブ”が発生することがあり、これが発生すると、再度連携して攻撃できる。1ターンに2回行動できるようなシステムだ。ちなみに連携率が200%を超えると、確実にオーバードライブが発生する。
術は発動させるのに詠唱が必要で、詠唱にはターンを使うが、オーバードライブ発生時はターン消費なしで術を発動できるのが非常に強力だった。
連携範囲のマスさえつながっていれば連携となる。
連携率が高まったことで、オーバードライブが発動。選ばれたメンバーがもう1度攻撃する。オーバードライブで攻撃する対象はおそらくランダムで、技・術は法則に則って自動で選ばれる。
技によって連携範囲や行動順が変わるほか、選んだ“陣形”によって連携率が変わったり消費BPが減少することも。いかに仲間と連携するのか、そしてどの敵を倒すのかを考えて戦っていくのが、非常に楽しいところだ。
連携やオーバードライブは、敵も使用できる。多数の敵に2回行動されようものなら、ピンチになってしまうだろう。それを阻止するために、敵を連携させないようにタイムライン上で割り込んだり、敵の行動順を遅らせる“バンプ”属性の技を使ったりと、戦略の幅が非常に広い。バンプで敵の行動順を遅らせれば、その後ろにいた仲間と連携できることも。行動順操作がバトルを左右するのだ。
また、特定の行動に合わせて技を放つ“リザーブ技”も存在。敵の攻撃に反応して、その直前に割り込む“インタラプト”や、行動した味方に追従して技を放つ“フォロー”などが存在。それらを組み合わせながら、有利に戦えるタイムラインを形成していくのだ。
タイムラインの前後2マス以内に敵味方が誰もいない場合は、“独壇場”が発生。ひとりで多数の技を放つ連携攻撃をくり出せる。そしてこの独壇場も、敵が使ってくることもある。狙って味方の独壇場を作り出せることもあれば、敵を残り1体まで追い詰めたのに独壇場が発生し、逆転されたなんてことも。バトルのアクセントになっている要素だ。
敵が一体になったのでトドメを刺せそうだと思っていたところ、独壇場が発動。
強力な全体攻撃を連発されてしまう。
余裕だと思っていた場面が、いきなり独壇場で“全滅”に。タイムライン上で敵を孤立させないことも重要だと学んだのであった。
ほかにも要素はいろいろとあるが、基本は“いかに連携をつなげるか”に集約されている。システムはやや複雑なので、慣れるまでは「バトルが難しい」と感じるかもしれないが、使いこなせるようになれば、唯一無二の中毒性の高いバトルが楽しめるのだ。
ボス戦や強敵との戦いは、やり応え満点。
育成しがいのある成長システム
バトルシステムもさることながら、成長要素も奥深い。レベルというものは存在せず、バトルなどを通じてステータスがアップしていくのは『サガ』シリーズおなじみの要素(なお、メカはバトルでは成長しない)。
装備は武器・防具(種族によって扱いは異なる)が用意されている。装備品はいつでもどこでも、素材さえあれば強化することができ、強化によって別のアイテムに変わることも。アイテムによって、強化の派生ルートは異なる。
強化していくと別の武器になり、武器のグラフィックも変わるのは、やはりうれしい。
また、技・術も装備することで使用可能になる(ただ武器を装備するだけでは攻撃できないので注意)。一度覚えた技・術は、自由に付け換えられる(メカのみ、技が装備品に紐づいているので、自動で装備される)。
さらに、“ロール”という、いわゆるパッシブスキルのようなものがあり、変更することで、ステータスが上がる、連携率がアップするなど、特殊な効果が得られる。
ヒト系種族は、オーソドックスな装備欄。
獣人などのモンスターは、武器と防具の変更ができない。
メカは装備欄の区分がないなど、独特な仕様。
武器は片手剣、両手剣、片手銃、両手銃の4カテゴリ。カテゴリの中でさらに細分化されており、片手剣ならば“細剣”や“斧”などが存在。片手剣であれば何を装備していても使える共通技もあれば、斧だけでしか使えない専用技などもある。ユニークなのが、剣と銃を装備していると“剣×銃技”、片手銃と片手銃装備で“二丁拳銃技”が使えたりすること。人間だけが閃く“我流技”なども存在し、区分はとても細かい。
種族の個性
独特かつ、多彩すぎるのが種族によって異なる成長要素。オーソドックスな“ヒト”といった種族の中でも人間・吸血鬼・騎士・廃人・短命種などが存在。それぞれの詳細は省略するが、廃人以外はバトル中に“ひらめき”で技を覚えることができるのが特徴。豆電球が飛び出す、『サガ』シリーズの代表的システムだ。
種族“人間”の中でも、術が得意な“魔女”や、魔女に仕える“従士”がいたりと、とても幅広い。
こう見えてヒト系種族。魔具を装備しているため、モンスターの技が使える。
基本、どのキャラクターもLPがゼロになるとバトルに参加できなくなる。LPはワールドを移動すると全回復するため、そのワールドごとに用意された命だと考えるといいだろう。
短命種はLPがゼロになると、“継承”が発生し、生前の戦いかたや技・術を引き継ぐことができる。“チャイルド”や“ヤング”などといった、バトルするたびに進む短命種の年代とも言える“短命ロール”も存在。短命ロールが進むたびに強くなるが、進むほどに最大LPが減少する。
短命種。
成長したが、LP最大値が下がっている。
ほかにも、武器と防具は己の身体のみで、倒した敵の技を使って戦う“モンスター”(“魔具”を装備すればほかの種族でも同じようなことができる)や、装備品によってくり出せる技が変わる“メカ”などがおり、とにかく種族ごとの個性がとても強い。このあたりは、ゲームボーイの『サガ』シリーズや、『サガ フロンティア』を彷彿とさせる。
主人公それぞれの物語
全体的な雰囲気はかなり明るめで、『サガ』シリーズらしいケレン味の効いたテキストとともに、コメディタッチなストーリーが展開されていく。少なくとも序盤は、重厚で壮大な物語というよりも、軽いノリで冒険をくり広げていた印象だ。
主人公たちはいろいろな目的をもって世界を旅していくが、自分の出発点となる世界を抜け出すと、連接領域からさまざまな世界を旅していくというのは共通している。ひとつの世界での出来事が終わると、新たな仲間が加入していくようなシステムだ。
また、主人公にはそれぞれ異なる個性を持っていて、それが冒険や成長要素の変化につながっている。今回の先行プレイで体験できた、3人の主人公を紹介しよう。
御堂綱紀
“クグツ”と呼ばれる人形をあやつる力を持つ、御堂家の一員。ミヤコ市で頻発する怪異現象を収めるために、さまざまな世界で精霊の力を求めて旅をしていく。
本作の顔とも言える主人公で、家業をこなすために冒険をしていくという、その目的もとてもシンプル。初期のパーティー構成もわかりやすいので、本作を始めて遊ぶ人に向けた、チュートリアルのような存在だと感じた。
“クグツ”は種族のひとつで、ヒトに近い性質を持つが、技の“ひらめき”はない。また、武器は1種しか装備できない。そんなクグツの特徴は、他者が技を使用した際、条件が合えば“写し身”が発生し、その技をコピーして習得できること。写し身は味方だけでなく敵の技でも発生する。狙って味方の技をコピーさせることもできるほか、敵の強い技を思わぬ場所でコピーしてくれることも。
クグツ自体はほかの主人公でも仲間にできるが、綱紀だけ、クグツの装備要素のひとつ“ソウル”を変更することが可能。敵を倒すとソウルをドロップすることがあり、ソウルそれぞれに異なる効果や技が備わっている。それらを自由に変更できるのが、綱紀の個性だ。仲間キャラクターは誰でもロールを装備できるが、クグツはそれに加えて、ソウルも装備できるのが特徴ということになる。
クグツの仲間たち。それぞれ個性を持っている。
敵が前のターンに使っていた技を……。
ピコーンと写し身!
御堂は冒険の始まりとなるミヤコ市のなまりなのか、京都弁のような口調で話すのが特徴。基本はマジメだが、あっけらかんとしている部分もありつつ、それでいてクグツたちを人形ではなく、大事な仲間として扱うやさしさも持ち合わせている。
冒険の中では、デスヴォイスを特技とするメイド・ドロレスと出会った。
出会った人々がどんどん仲間になっていく。
アメイヤ アシュリン
ミヤコ市で暮らす小学生くらいの女の子、泉ゆめは。その正体は魔女見習いで、一人前の魔女になるために人間界に送り込まれた。
変身すると魔女の姿“アメイヤ アシュリン”に。要は変身魔女っ子といった感じで、イベントシーンやバトルではアメイヤ アシュリンの姿で活躍していく。
ピカッと変身!
物語の序盤で何者かに魔力を奪われてしまい、アメイヤは魔力を取り戻すために奮闘。いろいろな怪奇現象の起きるミヤコ市の問題を仲間たちと解決したのち、さらに魔力を求めてさまざまな世界へと旅立っていく。
『サガスカ』に登場した、十二星神の1柱である、ヴァッハ神も現れる。
ヴァッハ神(コピー)が前触れもなく突然仲間になるなど、とてもコミカルにストーリーが描かれる。
アメイヤは“ネコ”を集めることでパワーアップしていくという、独特の成長要素を持つ。ネコはイベントで手に入り、その種類は非常に豊富。グラフィックもひとつひとつ用意されている。
ネコから得られるものはさまざまで、アメイヤ専用のネコ型の武器が得られることもあれば、術が使用可能になったり、シンプルにステータスが上がったりする。
ネコはそれぞれグラフィックが用意されていて、集めるのが楽しい。そしてカワイイ。序盤だけでも20以上のネコが登場した。
ネコ武器。見た目もかわいいものばかり。
初期の仲間も個性的で、ネコの使い魔である“ロロ”(モンスターに近い)、神の使いのような存在であるヴァッハ神(コピー)などがいっしょに戦ってくれる。
今回体験した3人の主人公の中でも、とくにコメディ色が強く、すごく明るいシナリオが展開されていった。
連接領域での移動は、序盤は歩くだけで長いものに感じるかもしれないが、のちに超高速移動も可能だ。
使い魔・ロロ。かわいい。でも声は超シブい。でもかわいい。
冒険の中では“最終皇帝”というワードも。
ディーヴァ ナンバー5
歌姫と称されるほど歌が得意な、女性型のメカ。しかし、あるとき禁じられた歌を歌ってしまったことで、歌唱機能や記憶を封じられてしまう。心を失った状態に近いディーヴァ ナンバー5は、人型のボディを捨てて、古いボディに自身を移す。
禁止の歌と知らずに、美しい歌を披露してしまうディーヴァ ナンバー5。
その代償に、歌う機能とメモリ(心)を消されてしまう。
付き添いのような存在だった王国異世界探検隊隊長・コンスタンティンは、それを見兼ねてディーヴァ ナンバー5を異世界探検のメンバーに抜擢。失った心を取り戻すために、ディーヴァ ナンバー5はさまざまな世界で冒険をくり広げていく。
これがディーヴァ ナンバー5の初期姿! これはこれでカワイイ。
美人な見た目に惹かれて主人公に選んだ人は、「こんな姿になっちゃうの!?」と驚くと思われるが、本作のメカ主人公枠が彼女。感情はモニターに表現された表情で見ることができるが、これはこれでキュートでカワイイ。
パーティーメンバーの属性がバラバラすぎておもしろい。
かわいい(^▽^)
ディーヴァ ナンバー5の個性はボディタイプを変更できることで、メカの仲間が加わると、その仲間と同じボディタイプに身体を変更できた。ボディタイプによって基本性能や専用技が異なり、それらを駆使して戦略を変更できるのがディーヴァ ナンバー5だ。
先行プレイの範囲では、“バトルタンク”の姿になることができた。いきなりいかつい戦車の姿になって驚いたが、ボディタイプ変更は会話シーンの見た目にも反映されるのでさらに驚き。予想以上に手の込んだシステムだった。
か、かわいくない! カッコイイ!
会話シーンもボディタイプで変わる。
初期パーティーメンバーとなる異世界探検隊の面々も、今回体験した3人の中ではいちばん個性的。オオカミのような獣人の“イマクー”、SFのようなサイバースーツに身を包んだ少女“ウェンズデイ”、植物系短命種“ブラー”、サムライソードを使う女性“ボウディカー”と、個性と世界観の幅がものすごい。
心を取り戻すために冒険するという、悲しさをはらんだディーヴァ ナンバー5。行く先々で待ち受ける困難や試練を受け入れていくディーヴァ ナンバー5の姿は、かわいそうなんだけれども、とてもかわいらしい。その後の物語がどうなるのか、元のボディは取り戻せるのか、とても気になるところだった。
もっとたくさんの世界を冒険したい!
冒険の楽しさや世界それぞれの物語も楽しいところだが、やはりゲームの根幹はバトルにある。難度は高めだが、システムさえ使いこなすことができれば、強敵にも立ち向かえるようなやり込み度の高さは、『サガ』らしくもあり、とても楽しい部分だ。
冒険の仕方も個性的なことが多い『サガ』シリーズだが、本作はスキャンして出現したヴィジョンに沿って行動すればいいので、やることは単純明快。一方で選択肢は幅広く、本筋とは関係ない展開もしっかり用意されている。
また、戦闘中の会話は細かく変化し、キャラクターの関係性を見てとれるのがうれしい。御堂家のクグツたちは、綱紀がピンチになれば躍起になって守ろうとするようなセリフを放つし、アメイヤの従士・加藤 忍は、ロロと仲がよくないようで、ロロがピンチになるとバカにしたような言動を取ったりする。
勝利後にステータスアップすると仲間たちが祝福してくれるほか、戦闘中に倒れた状態でステータスアップすると、その状態専用のステータスアップセリフを放つなど、細かな部分でキャラクター性が感じられるのがとてもいい要素だった。
ロロに小言を言う加藤。こういった描写が事細かに用意されている。
周回要素も存在するようで、遊び続けていくとどのような変化が生まれていくのかも楽しみなところ。『サガ』らしい尖った個性が盛りだくさんのタイトルゆえに、万人受けというよりは、好きな人ならとことんハマるタイトルになっていると感じる。バトルシステムにハマれば絶対に楽しめる作品なので、とくに高難度のバトルを楽しみたい人には間違いなくオススメだ。
物語のふんわり加減というか、コメディタッチな展開の数々は、『サガ』シリーズファンならば楽しく受け入れられるだろう(壮大かつ重厚なファンタジーを想定している人は、ちょっと肩透かしを食らってしまうかも?)。バトルはもちろん、世界観・ストーリーに関しても唯一無二の楽しさが待ち受けている。
※ステータスに“愛”パラメータはない。
『サガ エメラルド ビヨンド』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
『サガ エメラルド ビヨンド』(PS5)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
『サガ エメラルド ビヨンド』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp)
...以下引用元参照
引用元:https://www.famitsu.com/news/202404/03338510.html




![任天堂 【Switch】Nintendo Switch Sports(スイッチスポーツ) [HAC-R-AS8SA NSW スイッチスポーツ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1718/4902370549263.jpg?_ex=128x128)
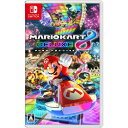






![コナミデジタルエンタテインメント 【Switch】桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 [HAC-P-ATKTA NSW モモタロウデンテツ]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1432/4988602173222.jpg?_ex=128x128)


![任天堂 【Switch】スーパーマリオブラザーズ ワンダー [HAC-P-AQMXA NSW ス-パ-マリオブラザ-ズ ワンダ-]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0075/4902370551587.jpg?_ex=128x128)


